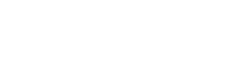〜AI時代に求められる“考える力”とは〜
「うちの子、覚えるのは得意なんだけど、応用になると手が止まってしまって…」
最近、保護者の方からよくこんな声を耳にします。
確かに、これまでの日本の教育は「知識をいかに早く・正確に詰め込むか」に重きを置いてきました。
でも、この“詰め込み型教育”は、AIが台頭する今の時代において、限界を迎えています。
なぜなら、知識の量やスピードでは、もう人間はAIに勝てないからです。
むしろ今、子どもたちに本当に求められているのは…。
「自分で問いを立てる力」「情報を選び、考える力」「答えのない問いと向き合う姿勢」です。
つまり、“問題を解く”ことより、“問題を見つける”力こそが、生きる力になっていくのです。
けれど、詰め込み型の教育ではどうしても、「正解を探す」思考に偏ってしまいがち。
答えを覚えることに慣れてしまうと、子どもたちは自分の意見を持つことを怖がり、「間違えないこと」ばかりに意識が向いてしまいます。
これでは、せっかくの個性や創造力が育たない。
どんなに才能があっても、「自分の意見を出していいんだ」という実感がなければ、それは発揮されることなく埋もれてしまうのです。
今こそ、家庭や学校で育てたいのは「何を学ぶか」ではなく、「なぜ学ぶか」「どう学ぶか」。
お子さんが何かに疑問を持ったとき、それを一緒に調べたり、考えたりする体験こそが“未来を生き抜く力”を育てます。
AI時代において、“人間らしさ”とは考えること。
そして、それを支えるのは、家庭での何気ない会話や、問いかけのひとつひとつなのです。