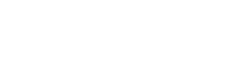「鎌倉幕府の成立は何年か?」
「大化の改新の中心人物は誰か?」
こういった問いが、学校での日本史教育の多くを占めてきたように思います。もちろん、知識は大切です。年号や人名を知っていなければ、話ができませんから。でも、ちょっと待ってほしいのです。
果たして、それだけを覚えて何になるのでしょうか?
小生が言いたいのは、日本史こそ「人間ドラマ」だということ。
事件には背景があり、人物には信念や葛藤がありました。
そこにこそ、本質があります。
たとえば…
坂本龍馬がなぜ命を懸けて新しい日本を創ろうとしたのか?
織田信長はなぜ、比叡山を焼き討ちするという非常手段を選んだのか?
西郷隆盛はなぜ明治政府と袂を分かったのか?
これらを理解せずして、なぜ日本史を学ぶ意味があると言えるでしょうか。
そこには「人間としての判断」があり、「時代を動かす決断」がある。
まさに、現代に通じる「経営者の決断」「リーダーの矜持」と重なる部分があるのです。
経営の現場に立っていると、歴史から学びたいと思う瞬間がよくあります。
決して「何年に何が起きた」というデータではなく、
「なぜその判断をしたのか」という背景にヒントがある。
歴史とは、過去の出来事の集積ではなく、「意思決定の連続」です。
つまり、日本史とは「人間の本質に迫る学問」であり、
「人の動機や思惑」を読み解く知的訓練です。
そして、そこから得られるものこそ、現代を生き抜くための“知恵”なのです。
教育現場には、もっと“問い”を増やしてほしいと思います。
「あなたが西郷隆盛だったら、どうする?」
「なぜ織田信長は比叡山を焼いたと思う?」
こうした問いは、想像力と共感力を育みます。
暗記ではなく、思考と感情で歴史と向き合うのです。
事実を知るのは第一歩。
しかしその先にある「意味」を知ろうとする姿勢が、
本当の学びにつながるのではないでしょうか?
我々大人ができることは、若い世代に「事実を超える視点」を与えることです。
ドラマを知り、背景を感じ、人間の本質に迫る。
そんな歴史の授業が、未来のリーダーを育てる土壌になると信じています。