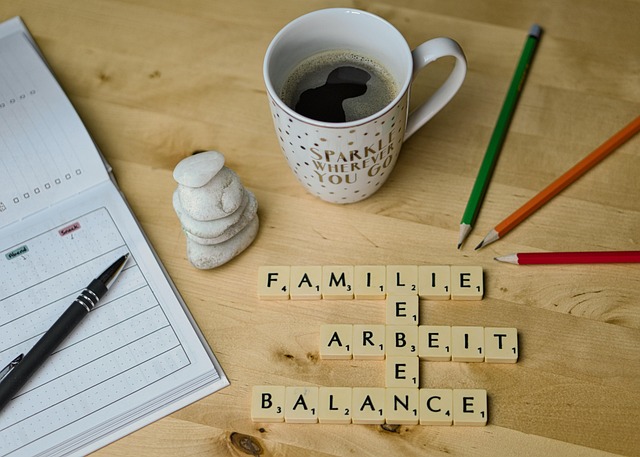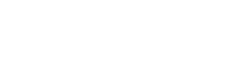「働くことは苦しいもの」「生活のために仕方なくやるもの」――そんな価値観を子どものころから植えつけられていないでしょうか。日本の学校教育や社会風潮には、どこか「働く=苦行」という暗黙の前提が流れている気がします。苦しいことを我慢した先にだけ報酬がある。そうでなければ働く価値はない…。そんな認識に縛られてしまっている人が少なくありません。
しかし、果たしてそれが“正しい働き方の教え”なのでしょうか?
私たちは子どものころから、「働くことは人に喜ばれ、自分も幸せになる営みである」という教育を受けるべきだったのではないでしょうか。なぜなら、働くとは本来、人の役に立ち、感謝され、その喜びを分かち合う行為だからです。働くことを通じて社会とつながり、自分の存在価値を確認し、人として成長できる。そこにこそ、仕事の醍醐味があります。
実際に、経営現場を歩いていると、活き活きと働く人と、ただ耐え忍ぶように働く人の差は歴然としています。前者は「働くこと=喜び」と心から理解している人たちです。彼らは結果として高い成果を出し、周囲にも良い影響を与えます。逆に「苦行だから耐えろ」という認識で働く人たちは、心身をすり減らし、会社にも社会にも貢献できない悪循環に陥ってしまうのです。
だからこそ、私たち大人には「働く幸せ」を子どもたちに伝える義務があります。親として、教師として、経営者として、次世代に教えるべきは「仕事は我慢の連続」ではなく「仕事は人と喜びを分かち合える大切な営み」である、ということです。
未来を担う子どもたちが「働くことは幸せだ」と思える社会をつくる。これが、私たち大人に課せられた最も重要な責任だと思います。
さて、あなた自身はどうでしょうか。今日の仕事に、喜びを見いだせていますか?そしてその背中で、次の世代に“働くという幸せ”を伝えられていますか?