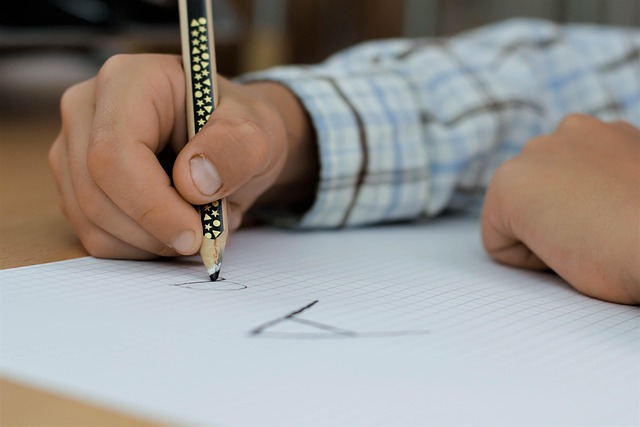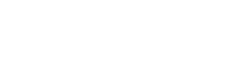近年、日本において 学習塾の倒産件数が著しく増加している という事実は、教育ビジネスのみならず、子ども・保護者・地域社会にとっても重大な警鐘だと考える。たとえば、2024年には学習塾(予備校含む)の倒産件数が53件に達し、過去最高を記録したとの報告がある。また、2024年1~10月だけで32件の倒産(負債1,000万円以上)が確認され、前年同期比で約28 %増という数字も示されている。
このような状況を受け、私は次のような主張と懸念を持つ。
1.構造的な逆風が厳しくなっている
学習塾が衰退・淘汰されつつある背景には、単なる景気変動以上の構造的要因が重なっている。
まず、少子化が最も明らかな要因である。6~18歳人口の減少は、生徒数の母数そのものを縮小させ、各塾の“取り分”を削る。教育市場全体が縮む中で、新たな参入も続いており、限られたパイをめぐる競争が過熱しているという構図だ。
次に、競争の高度化・多様化である。オンライン授業、映像教材、AI学習ツール、無料コンテンツの普及など、かつての “通塾型・対面授業” に依存する塾モデルだけでは対応が難しい領域が拡がっている。さらに、大手塾や資本力ある企業がITを導入・効率化を進め、ブランド力を武器にシェアを拡大していることも、中小規模塾にとっては強烈な競争圧力となっている。
また、固定費・設備投資・借入返済の負荷も無視できない。教室賃料、設備・通信インフラ、講師報酬、人件費などは、一定のスケールを持たないと収益性を維持しづらい。借入金の返済が重くのしかかるケースも見られる。
結果として、生徒確保(新規・継続)の失敗、採算割れ、回収不能というリスクが中小塾に集中し、倒産という最悪の結末を迎えるところが増えている。
2.倒産の拡大は教育の信頼・受講者の不安を誘発する
学習塾は、子どもの学び、将来の進路、保護者の期待といった極めてセンシティブな分野に関わる事業である。従って、塾の倒産が相次ぐことは、単なる市場の淘汰以上の、教育インフラとしての信頼の劣化を招きかねない。
たとえば、受験期直前での予備校の破たん(例:ニチガクの事例)は、生徒・保護者にとって深刻な混乱をもたらす。教室が突然閉鎖されれば授業継続が難しくなり、補填や代替策を探す時間も限られる。これによって、子どもの学習機会やモチベーションを損なう可能性がある。さらに、こうした事態が頻発すると、保護者・生徒側が「塾選びに慎重にならざるを得ない」心理が強まり、新規入塾に慎重さを帯びることになるだろう。
また、倒産件数が増えることで、塾業界全体のイメージがマイナスに傾くリスクもある。「塾が倒れるものだ」「信用できない」などといった印象が広がれば、生徒獲得のハードルがさらに高くなるという悪循環にもつながりうる。
3.将来に向けて求められる変革と打ち手
では、こうした逆風の中で、学習塾業界、あるいは地域の教育関係者・行政はどのような対応をすべきか。私は以下のような方向性を主張したい。
(1)差別化と付加価値化の追求
単なる「授業を提供する塾」から、「成果を出す/個別最適化する/学習支援まで伴走する」存在へと進化する必要がある。ICT/AIを活用し、生徒一人一人の習熟度・課題を可視化・フィードバックできる体制や、保護者フォロー、モチベーション維持支援、キャリア教育など、付加価値を含めた「塾+α」のモデルを構築すべきだ。
(2)共同化・統廃合・規模拡大/業界再編
小規模塾が単独で生き残る難度は高いため、地域で連携する、教務やバックオフィスを共通化する、複数塾の統合を図るなど、規模の経済を追求する動きが不可欠だ。大手資本と提携する、事業継承を視野に入れるといった選択も視野に入る。業界再編は、むしろ今後の健全化に向けて必要不可欠なプロセスになりつつあると感じる。
(3)リスク管理・健全経営の徹底
借入調達・返済計画、キャッシュフロー管理、人件費比率の最適化、設備投資の抑制、無駄な固定費の見直しなど、経営体質そのものを強化しなければならない。加えて、授業料先払い制の見直しや生徒・保護者に対する補填制度(教室閉鎖時の振替・返金対応など)を制度的に整えておくことは、信頼維持という意味でも重要だ。
(4)行政・地域支援の役割強化
教育という公益性の高い分野であることを鑑みれば、地方自治体や国が、塾経営の安定や教育格差是正の観点から支援すべきだ。例えば、資金繰り支援、業界統合支援、塾向けIT導入補助、共同プラットフォーム整備、倒産リスクを見据えた塾審査基準やモニタリング制度の整備など、政策による後押しが欠かせない。
4.まとめ:淘汰は進むが、教育機会を守る道を考えたい
確かに、学習塾倒産の増加は、「厳しい時代」の証左である。構造変化を拒む者は淘汰されるだろう。しかし、だからこそ、教育という命題を扱う業態である以上、単なる淘汰では済まされない。倒産増加を「悲観的な現象」で終わらせてはならず、業界・地域・行政が協働して 教育機会を守りつつ、次代にふさわしい塾のあり方を再構築する転換期 と捉えるべきである。
私は、教育を必要とする子どもたちに、信頼できる学びの場を提供し続けるために、塾側の変革と外部支援の拡充を強く訴えたい。そして、保護者・生徒・社会全体がこの課題を共有し、より良い学習環境の構築に向けて動くべきだ、という立場を主張したい。